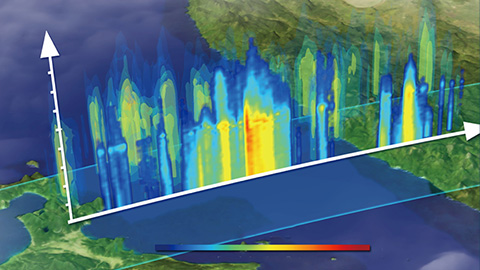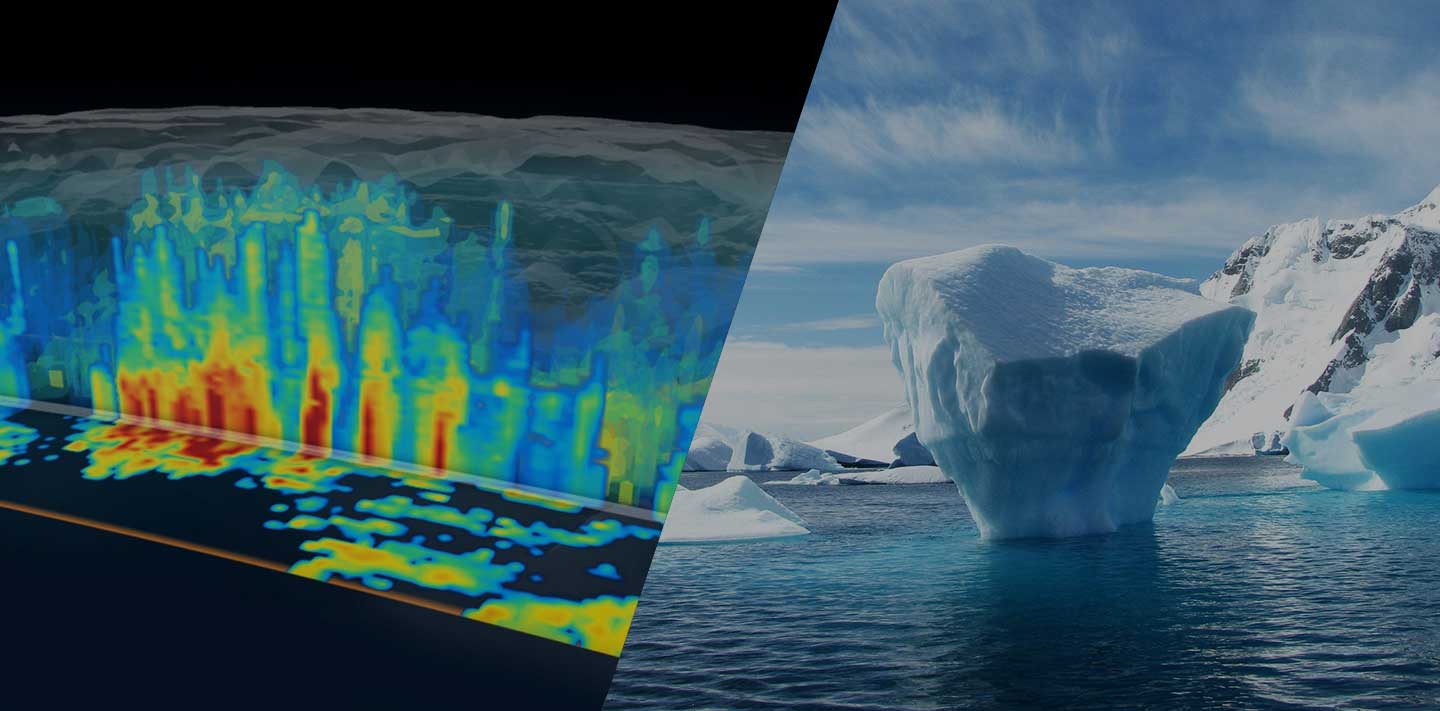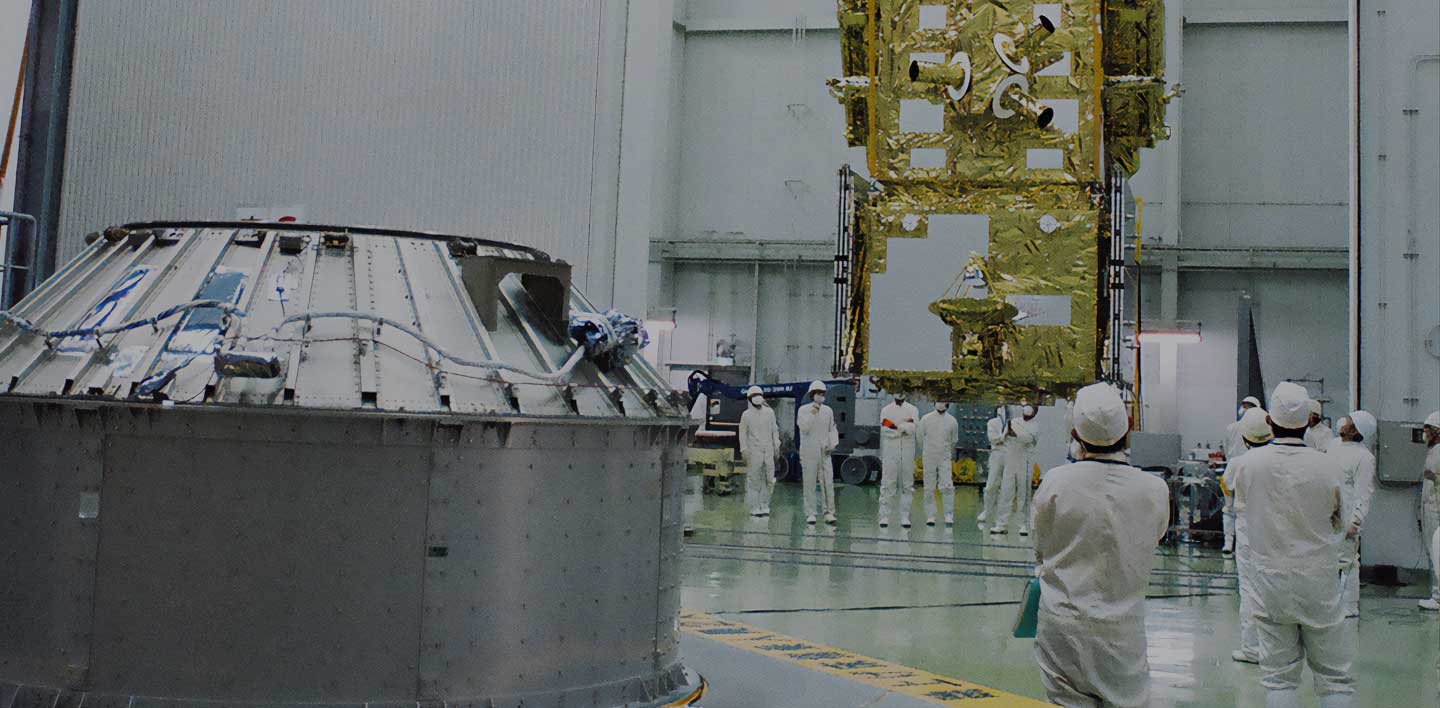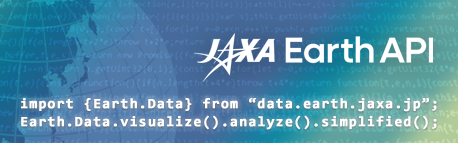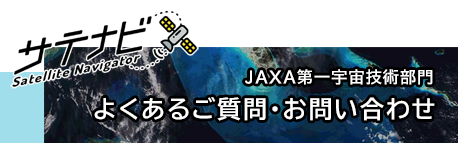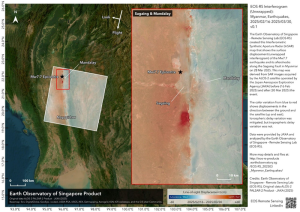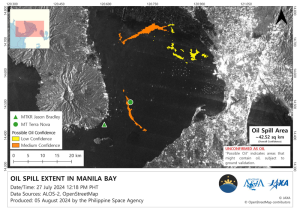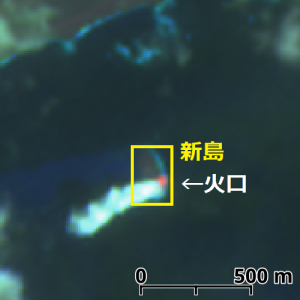災害
2023.11.30(木)
硫黄島南岸に出現した新島の衛星観測(第2報、12月13日更新)
1. 概要
- 【2023年11月10日】第1報の初版記事を掲載しました。
- 【2023年11月30日】第2報として11月27日の衛星画像を掲載しました。
- 【2023年12月13日】第2報に12月2、6日の衛星画像を記載しました。第2項の説明文を読みやすくしました。
硫黄島は東京から南へ1,200kmに位置する火山島で、北東から南西までの長さは約8kmです(日本周辺海域火山通覧第4版、海上保安庁)。2023年10月21日に、硫黄島南岸の翁浜沖における噴火(火山活動解説資料、気象庁)、により発生した新島について、再び成長が見られたため、第2報としてご報告します。硫黄島の詳細は第1報をご覧ください。
2. 再度の成長
11月8日以降、新島の成長が見られていなかったところ、11月29日には、新島が南北に500m以上にまで成長しました。南端には火口と推察されるくぼ地が形成されたと見られます(図1a、衛星「だいち2号」)。図1a内の黄色矢印の先に三日月形の明るい箇所が、くぼ地であることを示しています(霧島山(新燃岳)の観測事例でも見られています。)。図1aの矢印の先にある三日月形の明るい箇所は、衛星と正対する斜面が明るくなったと推察されます。今回は、衛星が西側を通過したため、西向き斜面です。西向き斜面が弧を描いていることから、その中心(三日月形の西側)がくぼ地であり、火口である可能性があります。
また、11月27日には、衛星「Sentinel-2」でも観測しており(図1b)、「だいち2号」と同様の新島形状と北北西へたなびく噴煙が認められ、引き続き火山活動が続いている様子が伺えます。
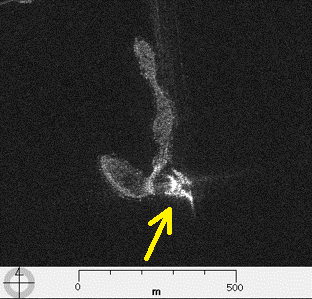

図 1:衛星「だいち2号」および衛星「Sentinel-2」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島(2023年11月27日観測)
3. 新島の成長(その2:12月13日追記)
さらに、12月6日には新島が南北に600m以上にまで成長していました(図2a、衛星「だいち2号」)。また、12月2日の衛星「Sentinel-2」による観測では、以前には見られた南端の噴煙が、今回は確認できませんでした(図2b)。
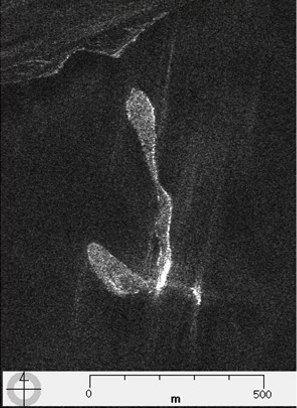

図 2:衛星「だいち2号」および衛星「Sentinel-2」が捉えた硫黄島翁浜沖の新島
このほか、軽石や火山由来の変色水など、複数の活動が観測されています。今後、得られた情報をご紹介します。
4. 関連記事
「だいち2号」観測による硫黄島の観測結果は、国土地理院からも報告されています。
なお、火山関連記事へのリンクは第1報に掲載しています
掲載年から探す
カテゴリーから探す
タグ一覧
-
#ALOS
-
#GSMaP
-
#GCOM-C
-
#公衆衛生
-
#エアロゾル
-
#データ提供
-
#陸
-
#地震
-
#大気
-
#海洋
-
#海氷・雪氷
-
#GPM
-
#DPR
-
#台風
-
#雨
-
#国際協力
-
#森林
-
#火災
-
#干ばつ
-
#GCOM-W
-
#シミュレーション
-
#GOSAT
-
#温室効果ガス
-
#インフラ
-
#ひまわり
-
#SLATS
-
#農業
-
#火山
-
#EarthCARE
-
#G-Portal
-
#AW3D
-
#水循環
-
#洪水
-
#Today's Earth
-
#NEXRA
-
#AMSR
-
#気候変動
-
#炭素循環
-
#API
-
#人文社会学
-
#土地利用土地被覆図
-
#環境問題
-
#速報
-
#GOSAT-GW