2025.07.16活動報告
SPACETIDE2025パネルセッション「商業宇宙の価値実現を加速する地理空間情報」開催レポート
2025年7月8日(火)、虎ノ門ヒルズフォーラムにて開催された「SPACETIDE 2025」にて、地理空間情報と宇宙産業の融合をテーマにしたパネルセッション「Unlocking Commercial Space: The Power of Geospatial Data/商業宇宙の価値実現を加速する地理空間情報」が実施されました。
本セッションでは、国内外のキーパーソンを迎え、気候変動対策やスマートシティ、インフラ整備、防災といった社会課題に、地理空間情報がどのように貢献できるかについて活発な議論が交わされました。
◆登壇者一覧
モデレーター
・杉田尚子(Naoko Sugita)|CONSEO事務局 / JAXA 地球観測研究センター 参事
パネリスト
・Ronda Schrenk|CEO, USGIF(United States Geospatial Intelligence Foundation)
・Ananyaa Narain|Vice President - Consulting, Geospatial World
・座間 創(Hajime Zama)|株式会社パスコ 衛星事業部 事業推進部 部長
・山崎 秀人(Hideto Yamazaki)|株式会社Tellus 代表取締役社長
◆セッション冒頭:今こそ「衛星データは地球規模の課題に立ち向かう重要なツール」
“Satellite data may not sound exciting as likes going to the Moon or Mars, but it plays a crucial role in addressing global challenges.”
冒頭、杉田は、「月や火星の探査ほど派手ではないが、衛星データは私たちの暮らしをより良くし、地球規模の課題に立ち向かう非常に重要なツールである」と指摘し、地理空間情報と衛星地球観測データの社会実装に向け、本セッションを開始しました。

◆Ronda Schrenk氏|地理空間データはグローバル課題に不可欠かつ当たり前の存在に
“Geospatial data is supporting everything from conflict monitoring to climate analysis”
Ronda Schrenk氏は、地理空間情報が国家安全保障や災害対応に加え、気候変動やサプライチェーン管理など、民間・公益領域でも不可欠な存在になっていることを強調されました。
特に注目している領域としてハイパースペクトル衛星を用いたメタンガス排出の可視化や炭素吸収源(森林)の観測などの事例が紹介されました。
また、データの量ではなく、そこからインサイトを導き出せるインテリジェントツール、並びにそのデータから意味を見いだせる技術スキルなどをもった人材像などにも触れられました。
また、スマートフォンでGoogleマップを使って目的地にたどり着くなど、私たちは無意識のうちに地理空間データを活用していることを例に挙げ、今後5年以内にはそれがさらに「意識すらされないほど当然の存在」になると述べました。
そして現実世界のあらゆる出来事は「ある場所と時間において」起こることを再認識する必要があると提言。特に「X・Y・Z・T(時間)」という4つの軸で物事を捉えることで、私たちは初めて世界を“3D+時間”として理解し、今何が起きているのか、そしてこれから何が起こるのかを予測する力を手にすることができると語りました。
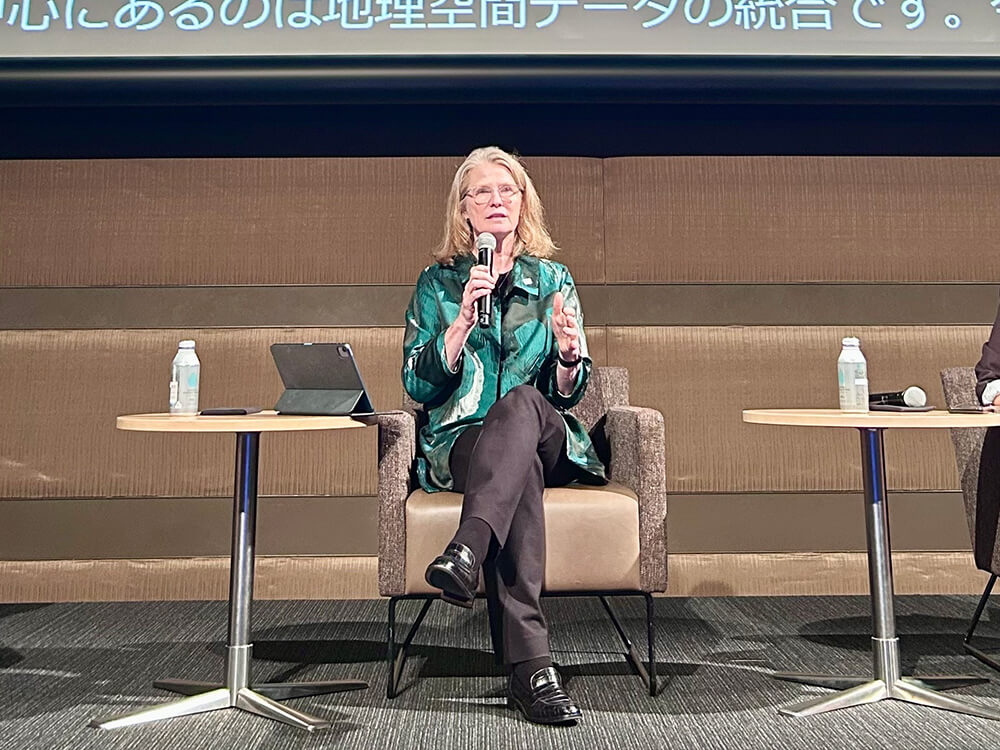
◆Ananyaa Narain氏|地理空間と宇宙は不可分であり、分野を超えた対話と連携が不可欠
Geospatial WorldのAnanyaa Narain氏は、地理空間産業と商業宇宙産業を取り巻く市場拡大や民営化の加速といった変化を紹介し、投資の軸がハードウェアからアプリケーションへ移りつつあると指摘しました。
気候変動、災害対応、インフラ、スマートシティといった分野が今後の注目領域であり、投資が進む可能性が高いことにも言及しました。
また、宇宙データと地理空間データは不可分な関係にあり、“Geospatial data needs space data as much as space needs geospatial to be commercialized.”と述べ、Googleマップを例に挙げながら、両者がすでに日常の中で一体化していることを示しました。
さらに、宇宙と地理空間、異なる分野のプレイヤー間での対話と連携が今後ますます重要になると強調し、サイロを越えた協働の必要性と、それを支える技術基盤やパートナーシップ構築の重要性に触れました。

◆座間 創 氏|現場実証を通じたユーザーとの共創の重要性
パスコの座間氏は、これまで手掛けた実証プロジェクトとして、電力需要予測や森林伐採の検出事例を紹介されました。
また、衛星画像から得られた3Dデータを活用し、インフラ構造物の劣化検知や電力インフラの設計支援などへと展開している事例を紹介し、ユーザーとともに実用的な地理空間ソリューションを創造していくことの重要性についても触れられました。
“This social demand for existing data and the increasing data of the satellite, this is going to be very nice to be a solution for the infrastructure.”
さらに、インフラモニタリングや災害対応の観点から、多くのGISなど既存データがすでに整備されていることに言及され、そうした既存データを教師データとして活用し、衛星データなどと組み合わせることで、効果的なソリューションにつながる可能性があると述べられました。今後の取組みとしてMarble Visionsによる高頻度での地球の3次元観測・可視化・デジタル地図活用を可能とする衛星観測システムについて触れられました。
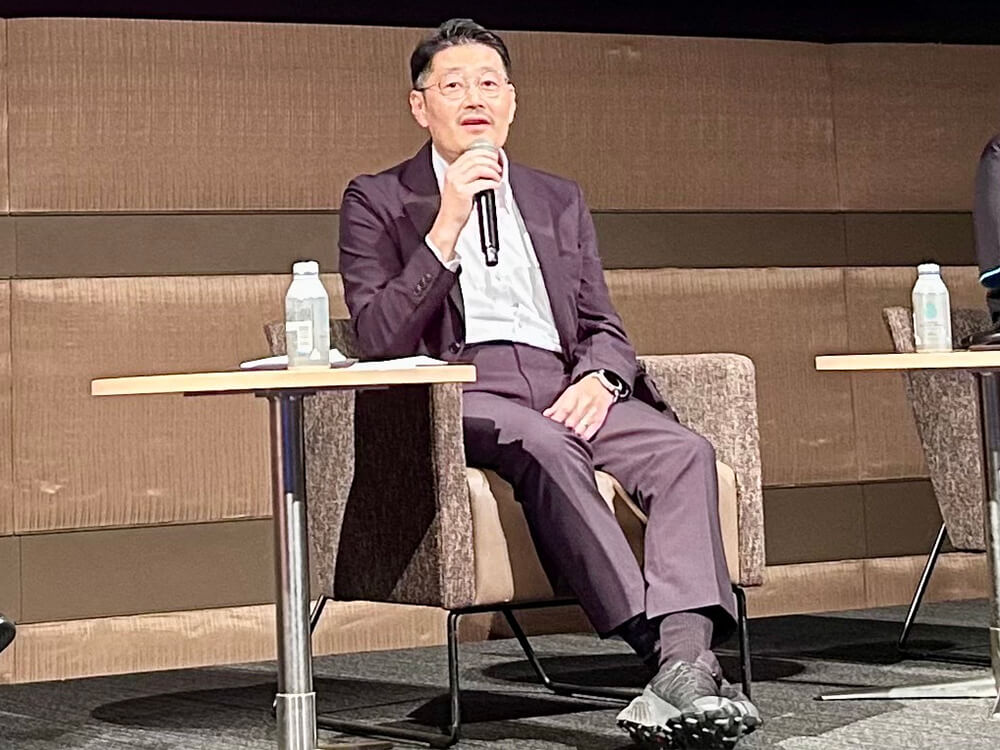
◆山崎 秀人 氏|AIとの協働と技術基盤・環境整備が求められる
Tellusの山崎氏は、自社が提供する衛星地球観測データのプラットフォームについて紹介したうえで、特定の観測地点に対し複数の衛星から観測データを取得・依頼できる新たなサービスを紹介しました。
“It's impossible for human beings to utilize all the massive amounts of data there. So we have to work with AI.”
今後ますます増加するデータ量に対応するにはAIとの協働が不可欠であり、人では処理しきれない膨大なデータを扱うための技術基盤・環境整備の重要性についても強調されました。
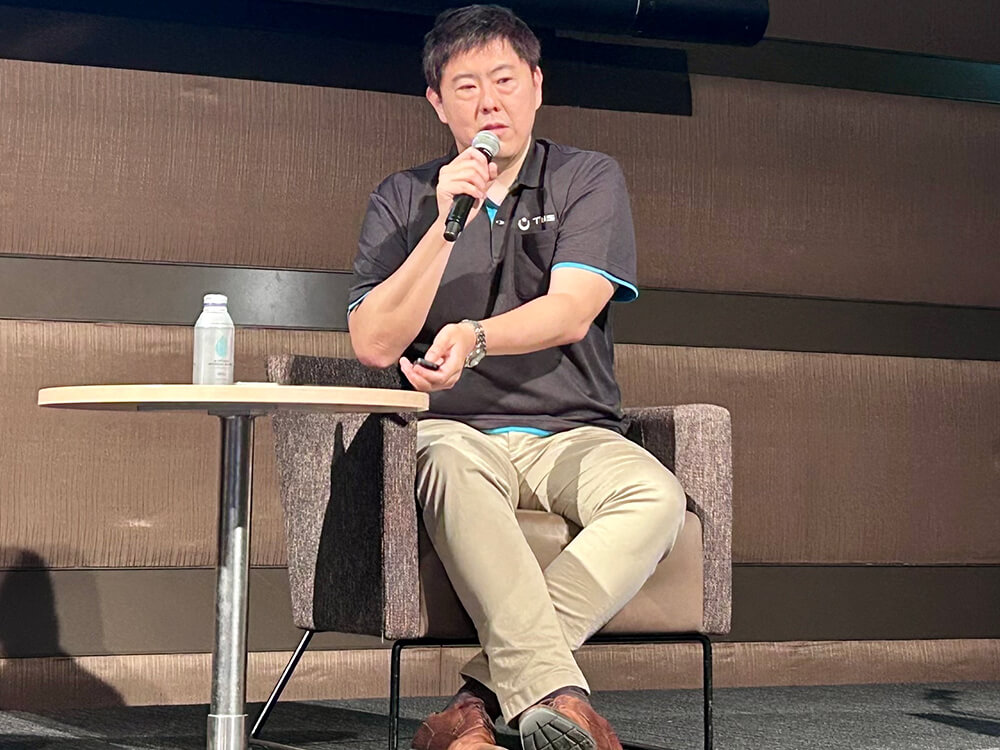
◆杉田 尚子|「情報産業」としての宇宙開発へ
CONSEO事務局 杉田からは、宇宙機関の従来の役割が製造業的な立場から変化しつつあり、現在では産学官およびグローバルなプレイヤーをつなぐ“ハブ”としての機能が強く求められていると語りました。
地球観測分野における産学官連携のプラットフォーム「CONSEO(衛星地球観測コンソーシアム)」の取り組みにも触れ、設立から約2年で会員数が300に迫るなど、日本国内での関心と広がりが着実に高まっていることを紹介しました。
“In Japan, space development is often seen through the lens of manufacturing, but we need to shift our perspective and start viewing it as part of the information industry.”
地理空間情報や衛星データの利活用を“製造業的視点”にとどめるのではなく、情報産業として再定義する視点の重要性を指摘。
また、今後は多様なプレイヤーの共創によって初めて社会実装が進む領域であるとし、産・学・官に加えグローバルな視点も含めたパートナーシップと対話の積み重ねが不可欠であると強調しました。

◆編集後記|横断的に繋ぐこと、継続して対話すること──社会実装の起点としてのCONSEO
本セッションを通じて繰り返し語られたのは、地理空間情報と衛星データが、すでに私たちの社会・経済活動の“基盤”として不可欠な存在になりつつあるということでした。
宇宙と地理空間は切り離せない関係にあり、気候変動対策、スマートシティ、防災、インフラ保全等といった、人類が直面する本質的な課題に対して、これまでにないインサイトと手段を提供できる可能性が技術革新により高まっています。
同時に、それらの力を社会で本当に使えるものにするためには、データや技術の積み重ねのみでは不十分です。衛星データに関わる産学官のプレイヤーに限らず、地理空間情報を軸に他産業の知見を持つプレイヤー、そして国や分野を越えた多様なステークホルダーと、共通の目的を見出し、地道に対話を重ねていくことが不可欠です。

そうした共創プロセスそのものを見通して、設計していくことが重要であり、CONSEOはその起点として、関係者をつなぎ、対話を生み出す“ハブ”としての機能を果たすべきであることを、あらためて強く感じました。
「見通せる社会」の実現に向けて、CONSEOはこれからも、技術と社会、宇宙と地理空間、分野と分野のあいだに立ち、すべての関係者の皆様とともに対話を積み重ねて、衛星地球観測データの社会実装を進めてまいります。