
農林水産業
農林水産業は、生命を支える「食」と、安心して暮らせる「環境」に直結する重要な分野です。少子高齢化のなかで、農地・森林・海域の効率的な管理が重要となっています。
衛星データは、土地の状況を、航空機やドローンより広範囲で把握し、整備・更新をしていくことができます。また、衛星センサによっては、土地の地表温や乾燥度、海においては海面温度等が計測できることから、農作物のでき具合等も把握でき、農林水産業の収益向上にも繋がります(図1)。

・農業
・林業
・水産業
<農業>
・農業気象情報衛星モニタリングシステム(JASMAI)
世界の主要耕作地の作柄判断を通じて国内外の食料安全保障に貢献するため、農林水産省は衛星データを活用して、国・地域ごとの気象・植生に関わる情報を、農業気象情報衛星モニタリングシステム(JASMAI)を通じて提供しています(図 2)。JASMAIはJAXAが技術移転をして農林水産省が構築したシステムであり、JAXAのGCOM-WやGPMなどの衛星データから作成されている気象(降水量、土壌水分量、地表面温度など)や植生に関わる衛星データが活用されております。

(引用:農林水産省 Webサイトより)
<林業>
林業は木材を生産しているだけでなく、森林を守ることによって、土壌内に水を貯え山崩れなどの自然災害を防いでいます。木が二酸化炭素を吸収し、酸素を放出することで地球温暖化対策としても重要な役割を果たしています。
JAXAの地球観測衛星「だいち」、「だいち2号」、「だいち4号」に搭載されている合成開口レーダ(SAR)による観測では、昼でも夜でも観測ができ、観測に使う電波は雲や雨を通り抜けることから、厚い雲に覆われている雨季のアマゾンの地表の様子も観測することができ、森林・非森林の状況を把握することができます。
また、「いぶき」、「いぶき2号」に搭載されている温室効果ガス観測センサでは、二酸化炭素やメタン等の温室効果ガスを観測することができます。
これら地球観測衛星のデータを活用することで、土地や大気の状況を把握・更新し、地球温暖化対策に貢献します。
・バイオマスマップ
バイオマスマップでは、1ピクセルあたり10m×10mという高解像度で、日本全国の森林における地上部の炭素蓄積量を把握することができます。
これまで人的・資金的に計測が困難であった小規模な自治体・企業・個人が所有する森林において、炭素クレジット(※)計算への貢献が期待されます。(図3)
※:炭素クレジット
森林の成長や省エネ機器導入によって、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの削減・吸収が行われた量をクレジット(排出権)として認証し、主に企業間で取引できるようにした仕組みのこと。

・JJ-FAST
JJ-FAST(JICA-JAXA熱帯林早期警戒システム)は、熱帯林減少を早期発見するシステムです。
現在は、ブラジル域を1.5ヶ月おきに観測した結果をもとに、1.5ヘクタール以上の森林伐採地域を検出することができます。ブラジル以外の国の過去(2024年3月以前)の検出結果もご利用いただけます。(図4)
地方当局は JJ-FAST の検出結果を既存の国土利用地図や伐採許可地図と比較することで、違法行為を効果的に特定することができます。

・SAR全球モザイク森林・非森林マップ
世界の森林の分布を調べることができるデータをダウンロードすることができるサイトです。
「全球PALSAR-2/PALSAR/JERS-1モザイク」はSAR衛星(レーダ衛星)が観測したデータです。
ダウンロードできる1つの画素のサイズは約25m四方で、概ね1年毎のデータが用意されています。
「全球森林・非森林マップ(FNF)」は観測データを森林・非森林・水域に識別されたデータです。(図5)
操作方法はこちらをご参照ください。

・全球マングローブマップ
全球マングローブマップ(The Global Mangrove Watch (GMW) )は1996年、2007-2010年、2015-2020年の11年間の全世界のマングローブ林の分布のマップをダウンロードすることができるサイトです。
マングローブ林は「海の命のゆりかご」と言われるように豊かな生態系を作り出し、大量の炭素を貯え気候変動においても重要な役割を担っていますが、沿岸地域での農業や養殖業の拡大による森林破壊などにより減少しています。
全球マングローブマップは、マングローブ林の範囲と変化に関する情報を提供することで、マングローブ林の減少を抑制することを目的としています。(図6)

・K&Cモザイク
K&C モザイクでは、森林起源の炭素量の把握を主目的とした「京都・炭素観測計画」を遂行するために作成された2種類のデータをダウンロードすることができます。
「PALSAR50mオルソモザイクプロダクト」は2007年~2009年の雨期と乾期、夏期と冬期の2回全球を観測し、年毎かつアジア・オセアニア域について作成領域単位で作成されたデータです。緑色に見えるところが森林、紫色に見えるところが伐採地あるいは森林でないところを表示しています。
「PALSAR500mブラウズモザイクプロダクト」は2007年~2011年の間にALOS/PALSARが観測したデータを、高速な処理によって閲覧しやすい画像にしたものです。この画像は、簡易的なモザイク処理(複数の画像を貼り合わせて一枚の画像にする処理)を施したものです。(図7)

・JASMES Image Analyzer
JASMES(JAXA Satellite Monitoring for Environmental Studies )で公開している、「しきさい」をはじめとした衛星観測による 全球の気候変動に関わる諸物理量が表示できるマップです。植生分布、植生乾燥度(水ストレス)、林野火災放射量、林野火災検知、蒸発散量などの植生に関する物理量以外にも、雪氷分布や短波放射量(日射量)など多岐にわたる物理量を表示できます。マップは自由に拡大・スクロールすることができ、2画面表示や、任意の地点における時系列グラフも表示することができます。(図8)

・しきさい観測画像 (GCOM-C) 宇宙からの紅葉
「しきさい」は多波長光学放射計(SGLI)を使用して森林や陸域の様子を250m分解能で高頻度に観測しています。「宇宙からの紅葉」のサイトでは2020年10月~11月のデータを使用し、雲を除くなどして合成した日本全域の紅葉の様子を見ることができます。地名をクリックすることで、紅葉が見られた日の観測画像を表示できます。(図9)

・GOSAT/GOSAT-2 EORC Monthly Global GHGs Map

北半球が夏の時期、SIFの値が高い(濃い緑色)地点が北半球に多く見られる
植物は光合成によって、光で水を分解し酸素を発生して、二酸化炭素を有機物に固定しています。その際、人間の目では光合成が行われているのか、行われていないのか判別することはできませんが、「いぶき」、「いぶき2号」は約1万色の色から、光合成をしている時に植物がだす太陽光誘起クロロフィル蛍光(Solar Induced chlorophyll Fluorescence「SIF」)を計測することで、光合成の活発さを定量的に評価することができます。
「GOSAT/GOSAT-2 EORC Monthly Global GHGs Map」ではプルダウンで「GOSAT SIF」、「GOSAT-2 SIF」を選択することで、2009年以降のSIFの値がどう変わってきているのか長期間の変化を見ることができます。
観測地点毎の詳細なデータは申請後にダウンロードでき、地図上でマッピングされたデータを見ることができます。(図10)
<水産業>
・水産業のスマート化
日本は四方を海に囲まれ、三陸・金華山沖は世界三大漁場に数えられるなど、昔から水産業はなくてはならないものとなっています。しかし、日本の水産業は、漁業生産量の減少や漁業就労者の高齢化、担い手の不足、さらには記録的な高水温が各地で発生するなど、様々な課題に直面しています。
そのような水産業を成長産業に変えていくために、スマート水産業への注目が高まっています。水産庁が推進しているスマート水産業とは、ICT、IoT 等の先端技術の活用により、水産資源の持続的利用と水産業の産業としての持続的成長の両立を実現する次世代の水産業のことです。例えば、海洋環境を見える化することで漁師の経験や勘をデータとして可視化し、漁業や養殖業の安定生産に貢献します。
「しずく」に搭載されているマイクロ波放射計や、「しきさい」に搭載されている光学放射計では、一度に1,000km以上の幅で海洋環境を観測することができます。人工衛星の観測技術は、遥か彼方まで続く海の状態を、均質かつ継続的にモニタリングするための無二の手段となっています。
・宇宙から海を見る
JAXAの地球観測衛星は、世界の海の水温や色を高精度で観測しています。
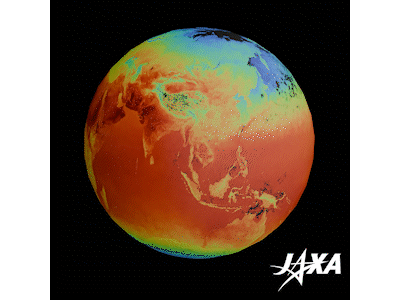
「しずく」(GCOM-W)は雲の下の海面水温も±0.5℃という高い精度で観測します。「しきさい」(GCOM-C)は雲の下の海は見えないものの、250mという世界最高級の分解能で海面水温や水の色を高精度で観測します。海の色の情報からは、濁りの指標である懸濁物質濃度や、植物プランクトン量の指標であるクロロフィルa濃度などの情報を得ることが出来ます。それらの観測データ(プロダクト)は個人・商用を問わず無償でご利用いただけます。

・水産業における衛星データの利用例
「しずく」や「しきさい」の観測情報は、水産分野の研究機関や全国の地方自治体で運営する研究機関である水産試験場などでご利用いただいております。(リンク:しきさいポータル)ここでは、いくつかの利用例をご紹介します。
①漁場探査
遠洋漁業に役立つ世界規模の海面水温や潮流、気象情報等を、インターネットを通じ提供するシステムが現在使われており、そこにはJAXAの地球観測衛星データも活用されています。一般社団法人漁業情報サービスセンター(JAFIC)の「エビスくん」は多くの沖合漁業の漁船に導入されており、漁獲量の増加、漁場探索時間と燃料費の削減に貢献しています。

(引用:一般社団法人 漁業情報サービスセンターWebページより)
②赤潮モニタリング
赤潮とは、特定の種類の植物プランクトンが海水中で異常増殖し、海水が着色する現象です。赤潮が発生すると、魚介類の突然死(へい死)や、海中の栄養塩が消費されて海藻類が生育不良となるなどの甚大な水産被害に繋がることがあります。そのため、赤潮の発生メカニズムの解明や詳細な分布把握が求められています。
2021年の9月から11月頃にかけて北海道東沖で例年になく広範囲な赤潮が発生し、水産資源に大きな被害をもたらしました。「しきさい」の面的情報は、現場観測情報と組み合わせて赤潮の全容把握に役立ちました。

③養殖
「しきさい」は高い分解能を有するため、内湾を観測することが出来ます。中でも懸濁物質やクロロフィルaの濃度情報は、プランクトンや魚貝類、藻類の餌の豊富さの指標となります。加えて、海面水温は海の生き物(魚や貝、ノリなど)の活動を大きく左右するパラメーターです。これらの情報は、漁場の把握のみならず養殖業でも役立ちます。

例えば、JAXAは広島県立総合技術研究所水産海洋技術センターと協力しながら、広島県のカキ養殖等の漁業者に水温データを配信しています。2024年の夏時期から「しきさい」の観測データを追加し、それまでの点の観測から内湾の海洋環境の面的な把握に活用されています。(リンク:広島県立総合技術研究所水産海洋技術センター)

さらに、JAXAと佐賀県有明水産振興センターで協力し、2024年の秋時期から衛星のクロロフィルa濃度観測情報を高頻度で漁業者に配信しています。現場観測情報を前提とした、赤潮の全容把握への貢献が期待されます。(リンク:佐賀県有明水産振興センター)

④藻場観測
2011年まで運用していたJAXAの「だいち」(ALOS)に搭載された高性能可視近赤外放射計2型(AVNIR-2)などの光学衛星画像は、藻場のマッピングに役立ちます。現在も、ESAのSentinel-2という衛星や、商用光学衛星が用いられています。藻場を取り巻く海洋環境(海面水温や懸濁物質濃度、光合成有効放射など)は「しきさい」が観測しています。

(観測日2007年9月11日)
⑤流れ藻
JAXAの「しきさい」は海面を漂う流れ藻を観測し、観測データを準リアル配信しています。ブリの稚魚は流れ藻を住処とすることがあり、もじゃこ(藻雑魚)と呼ばれています。ブリ養殖を行う上で、種苗として天然のもじゃこを採捕する必要があることから、もじゃこ漁における流れ藻情報の利用が期待されています。(リンク:流れ藻モニタ)

⑥気候変動
2023年は過去に例を見ない高水温を各地で観測し、気候変動に対する世界中の注目が高まりました。(リンク:気候変動2023)

「しきさい」は、衛星観測データから平年値(気候値)を作成・公開するとともに、平年値との偏差情報も配信しています。この情報を基に、海面水温やクロロフィルa濃度がいつもよりどの程度異なっているかを面的に可視化でき、気候変動適応に向けた利用が期待されています。
・衛星データを使う
ご紹介した衛星データは、以下のサイトより閲覧・入手いただけます。
「しずく」の観測プロダクト
データの閲覧:AMSR Viewer
データの入手:G-Portalなど
「しきさい」の観測プロダクト
データの閲覧:JASMES Image Analyzer
内湾環境:GEE版内湾モニタ
データの入手:G-Portalなど
「だいち」の衛星画像(AVNIR-2)
データの入手:https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/dataset/ori_j.htm
研究者向け情報
GCOMデータ画像化手順: https://youtu.be/9hixQL72K_U
・まとめ
このように、農林水産業における情報収集を行う際に、衛星データが活用されています。今まで人や航空機で行ってきた作業を、衛星データを併用もしくは代替することでより効率的に実施できることが期待できます。また、衛星データと他のデータを組み合わせることで、Society5.0やデジタルトランスフォーメーション(DX)といった社会の実現に、貢献していきます。


















